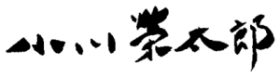ティーレマンの事、何度目かの。(1) (2011年05月08日)
(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2011年05月08日より)
先日、ティーレマンに就てEMさんといふ方から、投稿を頂戴した。その少し前に、畏友石村利勝君もメールでティーレマンの感想を書いて送つてくれた。彼は、大震災の最中、氣遣ひのメールを度々寄越してくれた。首都圈にゐて、家の近所の平穩無事な印象と、原發の爆發の映像や電車の全面的な停止、一方で極端に危機を煽る情報が錯綜としてゐたあの地震直後、遠方の友の聲は、氣強く感じられたものだ。「友あり、遠方より來る」ではなく、「友あり、遠方よりメール來る」といふ譯だ。
さて、以下、まづEMさんの投稿を御紹介して、それについて自由な感想を書きながら、興に任せて、石村君の引用もさせてもらつて、稿を進めてみることにしようか。
「いつもブログを拝読しております。
小川さんの適切な文語体は他の似非文語体にいらつかされることなく少々読みづらいですが適切な評論と納得させられることが多いし、わが意を得たりと思うことが多くあります。
さて今回コメントさせていただこうと思ったのは、ワレフスカのことが知りたく、某ブログにたどりついたところ、そこのティーレマンが書かれているところに小川さんが反論のコメントを載せられていたことがきっかけです。
小川さんのティーレマン評に啓発されてベートーベン、ブルックナーを聞いていますが、(FM録音、TV録画)どうも今一歩楽しめません。唯一ウイーンPO来日のブルックナー7番は良かったと思っています。
私にとってティーレマンは何と言ってもワグナー!それも5年間にわたるバイロイトの指輪です。これについては自分にとっては最高の演奏と考えております。聴くたびにこれ以上の演奏があるかと思いながら聴きました。昔の歌手のようにスケールの大きな歌手はいませんが、リンダ・ワトソンも健闘しています。
歌手陣に対するティーレマンの手腕は素晴らしい。精妙、豪腕、こうあってほしいと思うことを実現してくれると言えばよいのか・・・。
神々の黄昏の4幕目を昨日車で聴きましたが、ラインの乙女の会話からジークフリートの死、葬送行進曲からブリュンヒルデの登場、自己犠牲、ラインの氾濫、終幕に至る見せ場の連続に何と雄弁な音楽が鳴り響いてくることか。感歎の言葉しかありません。
自分としてはティーレマンはこれからだと思います。字数制限があるので此れまで。」
懇切なご意見で、讀んでゐて大變嬉しかつた。ありがたうございます。
さて、私の、ティーレマンに就ての考へは、今まで書いてきた通りなので、委しく繰返すことはもうしない。ブルックナーやベートーヴェンの素晴しさを書いた場合が多いのは、生演奏でそれらに觸れた經驗が觸媒になつてゐるからで、出來榮えに波があるのは間違ひない。尤も後で述べるやうにベートーヴェンやブルックナーでいつもホームランを打つのはフルトヴェングラーでも無理だつたこと、私見では、ティーレマンのベートーヴェンの(海賊盤で聽いたウィーンフィルとの)「第5」から「第8」、グラムフォンのブルックナー「第5」は、フルトヴェングラーやチェリビダッケを凌駕する程、私には魅力的である。たゞし、EMさんの書いてをられる通り、現時點でのティーレマンが、ヴァグナーに於いてとりわけ傑出してゐるのは、間違ひないだらう。
今、レコードを聴くことが殆どできない生活状況にあるので、EMさんご指摘の《指輪》については、残念ながら後日、じつくり聽き直す機會を見つけてから改めて議論したいと思ふが、その代はり、例へばグラムフォンから出てゐる《トリスタン》。これは、世界的にも評價のさほど芳しいレコードではなかつたやうだが、私は、すつかり當てられたものである。歌唱とオーケストラが、音の上での魅力ではなく、意味の次元で高度に滲透しあふといふこと。まさにフランスの象徴派詩人たちが眩惑され、言葉で模倣したところのヴァグナーの實質。その高い達成が、こゝでは易々と實現出來てしまつてゐるからだ。
これは戰後のヴィーラント體制の脱ゲルマン路線の中で、ベーム、カラヤン、クライバーらの誰もが、結局、實現できなかつた事である。勿論、これは彼らの才能や、美學上の流行にとどまらない根深い問題であるから、ティーレマンとの間に簡單に優劣を持込むのはいましめるべきなのだらう。ドイツ音楽の崇高さとナチズムを生む心性――ハイデガーの哲学、フルトヴェングラーのヴァグナーなどが表象し、マンの《ファウストゥス博士》が提起した重大なパラドクス――そのパラドクス自體をなかつたことにしなければ、そもそもヴァグナー演奏を存續させ得なかつた戰後といふ時代の壓力が、カラヤンらの演奏スタイルを作り出した一面は否定できないからだ。もし、1970年のカラヤンがバイロイトでゲルマン色そのもののヴァグナーを演じたとすれば、それは、三島が自衞隊で切腹するのと殆ど同質の、「戰後」への強烈な撲り込みを意味したことであらう。そしてカラヤンやベームが三島由紀夫でないのは、言ふまでもない。
さしづめ、アメリカ人バーンスタインによる《トリスタン》レコードなどは、さうした時代の壓力の生んだ眞面目なカリカチュアと呼ぶことが出來るであらう。バーンスタインは、この曲に、濃密な感情上の同化によつて迫らうとするが、音響を意味に轉化するあの千變萬化の和聲と音色の形而上學を驅使する力がない。だから、感情の襞に、理で迫らうとする。音が説明の手段に墮してしまふ。音樂は恐ろしく粘着質だが、粘れば粘るほど、かへつて單調になる。バーンスタインの啓蒙的な知性と、単純化された情念の二元論は、《トリスタン》を半音階だらけの《ウエストサイド》にしてしまつてゐるのである。だが、《トリスタン》は、そのやうな分析可能な感情のをはつたところから始まるのであり、それが、どのやうに危險な人間の原罪と隣り合せなのかといふ問ひこそが、戰後封印され續けてきた當のもの、そしてそれに向合ふことこそが《トリスタン》を演奏する意味だつたのである。
ティーレマンは、バレンボイムとともに、それぞれ違ふ方法と資質に立ちながらも、そしてバレンボイムの場合には60台に入つてようやく達した質に、40代の内に、到達してゐる。彼らが二人とも、ヴァグナーの、夜の世界、無限に曖昧で危險な形而上學の世界を囘復したのはどうやら間違ひないやうである。たゞし、バレンボイムの、中東和平やドイツの傳統と前衞音樂との共存に見られる、音樂の力への信頼が、彼の《トリスタン》をどう規定してゐるのか、一方のティーレマンの《トリスタン》が囘復した意味は、1930年代までのヴァグナー演奏の技法の復權に過ぎないのか、それ以外の意味があるのか、かうした問ひとは、さう遠くない將來、じつくり対決してみたいと思ってゐる。
ティーレマンのヴァグナーでは、もう一つ鮮烈な記憶に残つてゐるのが、ウィーンでの《マイスタージンガー》の映像作品。これは、この曲の演奏史を塗り替へる絶對的な高さに達してゐると思はれるし、そのことはDVDで容易に確かめることが出來る。第1幕への前奏曲が既にたゞならない。出出しが、まるで大團圓であるかのやうな、掟破りの濃密な昂揚を聽いてゐると、一體これからの6時間をどう持たせるつもりなのかと心配になる程だが、そんな心配は、御祈りの場面への轉換の見事さで、一氣に腦裏から去つてしまふ! 室内樂的な靜謐と親密さによつて、音樂はオランダの繪畫のやうなあぢはひに瞬時に轉ずるからだ。このコントラストにこそ、この作を單なる歌合戰の喜劇ではなく、民族の聖なる物語と化するモニュメンタルな力の秘密があるのだらう。それにしても、あらゆる細部が、これほど生き生きと意味を擔ひ、音樂と演劇的意味とが互ひを引出ながら、一切だれることのない《マイスタージンガー》、そして最後の昂揚が、6時間の時間を乘せて、聽き手の限界を超える超越的な法悦に達する集中力の持續には、言葉も出ない。この感想はEMさんの《指環》への感銘と、さう遠くはないはずである。(この項續く)