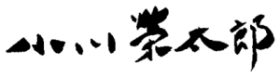批評家の手帖 (二)2017.1.11
子規が「貫之は下手な歌詠みにて、古今集は下らぬ集に候」と暴言を吐いて以来、130年経つても『古今』の復権は未だならずといふ有様だが、古今集には、萬葉的絶唱や、家持や後の新古今の絶美とは違ふ、九十九織りの美のなだらかさがあり、私は全く読み飽きない。一首ごとの感銘や巧拙は殆ど気にならず――圧倒的な歌は余りないが均等に良歌が多い――短か物語のやうに続く世界が楽しい。ヴェルサイユ宮殿や万里の長城がなくとも、又雄大な山系や大海原に息を飲むわけでなくとも、京都を歩き続けるのが楽しいやうに。
が、さうした美の玉手箱として以上に、古今集には国語表現の決定的な一歩目としての位置がある、そこを我々は見直すべきではあるまいか。古今集時代に仮名表記が確立したが、当時仮名は「女手」と呼ばれてゐた。つまりあの頃、「日本語」は、政治は元より文化の主流でさへ、まだなかつた。漢詩文が公式の言語であり、表記であつた。実際、嵯峨天皇時代までの勅撰詩集は全て漢詩集である。古今集がその流れを決定的に日本語側に引き寄せるが、それは美意識や文化的な意味での国風の濫觴といふ美学上のパラダイム転換に留まるものではない。
萬葉集を読んでゐると、そもそも語彙や人名からして、日本以前の日本と感じる事が多いが、古今集を読み進めてゐると、そこに現代日本語の源流を感じる事が多い。語音と仮名がやうやく確立し、それに応じて語源的な語の意味がこの頃ほぼ定まつたと感じる。その意味で、古今集は単に王朝美学の粋といふ事ではなく、今日我々が考へてゐる日本語の国語表記、国語表現の最初の高度な安定と見做すべきなのである。
子規、あららぎ、小林秀雄と続く古典に近代藝術を発見する道とも、保田の尊皇や折口の多分に想像的な古代蘇生とも違ふ、『古今』からの日本の再発見をなした人はまだゐない。