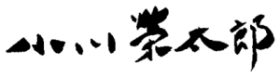ワレリー・ゲルギエフ コントラ ダニエル・バレンボイム ストラヴィンスキー作曲《春の祭典》小川榮太郎(2008年05月05日)
.jpg)
(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2008年05月05日より)
《春の祭典》―この曲が、20世紀クラシック音樂の古典として定着して、既に久しい。なるほど、才氣煥發、音樂史に新たな表現を持込み、しかも、それが、耳に、無類に面白い出來榮えに達してゐることを否定するつもりはない。だが、それでもなほ、このやうな音樂が、「天才」の「傑作」とされてゐるといふ事實は、20世紀ヨーロッパの、文明と藝術の、本質的な衰弱と荒廢の根深さを示してゐるといふ直觀を、私は捨てる譯にはゆかない。
このやうな發言は、ウルトラ保守主義者か、藝術音癡の全體主義者―「頽廢藝術」を認定したナチスや、社會主義リアリズムに反する前衞藝術を、ブルジョア的低徊と見たソ聯指導部―の言ひ分だといふ考へ方には、簡單に反論出來るだらう。第一に、私は、こゝに衰弱と荒廢を見ると、一個人として發言してゐるだけで、今後も、政治權力の側から、これらを彈壓するつもりはなく、また、そのやうな彈壓を是とするつもりもない。第2に、私は、全體主義の立場からでなく、1人の人間として、藝術の“主流”、藝術の“權威”が、このやうな方向を無條件に肯定する傾向に、直觀的に誤謬を感じ、その誤謬の直觀を、纏まつた思惟に高めることを、20世紀の主要な美學や批評が、全く手を着けなかつたといふ事實に、寧ろ、靜かに驚いてゐるだけである。
なるほど、ストラヴィンスキーに於て、音樂が新たに獲得した美學と技術とは、生半可なものではない。少し耳を傾け、多少でも作品を分析してみれば、それは、誰にも明らかなことだらう。だが、藝術の知的な意味での新しい展開や、天才的な斬新さなどが、そもそも人間にとつて、それ程尊重すべきものなのか。
植物を育てるのに、音樂を聽かせると成育に差が出るといふのは、今では、實證された事實だが、成育に最もいゝのがモーツァルト、成育するどころか枯れてしまつたのが、シェーベルクとヘビーメタルの音樂だつたといふ實驗結果を、昔何かで讀んだことがある。無論、音樂は、植物を育てる爲にあるのではない、須佐之男の號泣にも、青山は爲に枯れ伏したではないか。――私は屁理窟が得意だから、言葉では、どんな綾も作れるといふことを、身を以て知つてゐる。だが、聽かせれば植物が枯れるやうな音樂を、特に偏愛する理由も、また、私にはない。音樂に就て論ずる者の知的な虚榮として、或いは單なる好奇心から、或いは、それが音樂史上の傑作とされてゐるといふ理由だけから、その音樂を傾聽する程、藝術史や、アカデミズムのお説を有難がつて生きる必要もないだらう。
ヤスパースがかつて述べた人類史の樞軸となつた諸宗教と思想―佛教、儒教、ギリシア哲學、キリスト教―は、全て、藝術に關しては、それぞれに、嚴しい限界を設けてゐる。近代後期――ベートーヴェン、ゲーテ以後――のやうに野放圖に、藝術の成果を神聖視などしてゐない。對話篇を見る限り、プラトンが、概して音樂に敵意さへ持つてゐたことは、明白である。孔子は、廣い意味で音樂家であつたが、人心に與へる音樂の影響には注意してをり、インモラルな“頽廢音樂”は、これを嚴しく排擠してゐる。ベートーヴェンやゲーテの藝術の神聖化は、寧ろ、彼ら自身が、藝術を倫理的に高め得たとの自負と固く結び付いてゐるので、藝術と倫理性の結合を、勸善懲惡風の甘い前近代の迷妄と嗤つた、19世紀後半からの、藝術至上主義とは、寧ろ、その内的な志向は正反對だつたと斷じて構はない。
前置が長くなつた。《春の祭典》は面白い音樂である。音樂的な分析能力にたけた人間にとつては、知性を刺激すること夥しいであらうが、さうした能力と訓練に缺ける私のやうなたゞの音樂好きにとつても、まことに絶妙な、感官と知性への興奮劑である。だが、感官への絶妙な刺激は、現代生活には、無數にある。コカ・コーラも、コカインも、マクドナルドも、酒も煙草も、えびちやんのビキニ姿も、感官を刺激する。《春の祭典》は獨自の音樂的知性の勝利だが、えびちやんの華やかな笑顏と驚異的な腰周りの均整が、自然の造化力の一層の勝利、一層の價値、一層の永遠ではないと、では、一體誰に斷言できるのか。
私は、1980年代に流行したポストモダニズムは、狡猾で、近代が一層自身に淫するだけの、最惡のモダニズムに過ぎないと考へてゐるが、だからと云つて“近代の超克”が不要だとは思つてゐない。大きな成果を擧げた近代は、等量の負を我々にもたらした。藝術とアカデミズムの極めて異常な神聖化と社會化(!)も、その1つだらう。奇妙に神聖化された擧句、これまた極めて奇妙な仕方で、藝術は、チャップリンの《モダンタイムズ》風の齒車に組込まれてしまつた。現代、バッハの屬した社會の、小さいが確實な場所は、藝術家から失はれたが、ランボーやヴェルレーヌの捨て身の奔放を生きる天才のるつぼたる場所もまた、なくなつた。教育システムと出版システムとが結託して、凡庸な人間のシステムへの組込を推進しながら、神聖にして犯すべからざるアカデミズムと藝術の、すつかり形骸化した聖域を、奇妙に守つてゐる。凡庸な指揮者の振るベートーヴェンは「惡」だと云つたのはフルトヴェングラーである。凡庸なベートーヴェンを聽くくらゐなら、遙かに、心が快活になり、氣が晴れる音樂は、世の中にごまんとある。どさまはりの演歌でも、甲高い聲で歌はれる流行歌でも、心の痛手には、ヘボなベートーヴェンよりはずつと滿腹感があり、明日への元氣にもなるだらう。人生と何のつながりもないクラシック音樂、人生に何の力をも、思索と言語表現の喜びをも、與へない哲學や文學、知性が味はひを失つて情報に墮したアカデミズム、そんなものの何がありがたくて、人々は、それを社會システムの中でまはし續けてゐるのか。人生に直に働き掛ける倫理的な力を失つて、「高級化」したクラシック音樂なるものに、何の價値があるのかといふ問ひによつて、徹底して淨化されなほさぬ限り、その本當の、更生はおそらく困難であるのかもしれない。
……久しぶりに、本題に入れぬまゝ連載の形をとることにする。明日中には、演奏評に及んで、この一篇は仕上げるつもりである。(この項了)