パリ国立オペラ引越公演『トリスタンとイゾルデ』7月31日オーチャードホール(1)(2008年8月5日)
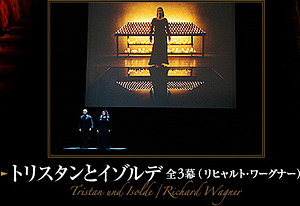
(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2008年08月05日より)
指揮 セミヨン・ビシュコフ/演出 ピーター・セラーズ/映像 ビル・ヴィオラ/ トリスタン クリフトン・フォービス/マルケ王 フランツ・ヨーゼフ・セリグ/イゾルデ ヴィオレッタ・ウルマーナ/クルヴェナール ボアズ・ダニエル
今日は惡口を書くので、公演に感銘を受けた方は、讀まれない方がいゝだらう。何が對象にせよ、惡口を讀むのが厭な方も、讀まれない方がいゝ。私は、人を襃めるのが好きな人間で、このブログでも過去に澤山の優れた音樂家を、賞讚してきた。惡口は書きたくないが、批評の責務は、時代への證言と思ひ、仕方なく書く。今囘の上演は、試み自體が不眞面目だから、聽衆の一人として許しておく譯にはゆかないのである。
あゝ、理窟はどうでもいゝ、バレンボイムの『トリスタン』が又聽きたい。家に歸つたら、フルトヴェングラーとクライバーとティーレマンのトリスタンレコードを連日立て續けに聽いて、渇きを癒さう。さうだ、バレンボイムの『トリスタン』も、マイヤーとイェルザレムと組んだ新しい方が、もう直ぐDVD化される。以前衞星放送で見て、ポネル演出の頃とは格段に素晴しい指揮振りだつた記憶がある。昨秋の生演奏のやうな歴史的な名演とまでは行つてゐないかもしれないが、これも樂しみである。
さて、公演評だが、何ともちぐはぐな上演であつた。歌唱は概して立派で、指揮も惡くはない。全てをぶち壞したのは、“話題の”新演出、いや、話題の映像演出である。幸せな事か不幸な事か知らないが、今日、文化上、話題になるものゝ多くは、ガラクタだと斷じて宜しい。話題にする人間と、興行主とが、つまり、評判と、その元になる素材とが、同じ人間の企圖になるといふ仕組に、文化や藝術が領略され、既に久しいのだから、これは考へるまでもなく當然の話である。話題にすれば儲かる、話題にすればそれだけで名聲の手蔓になる、なるほど、その通りで、要するに、興行主と評判の煙を煽る人間が同じ穴の狢なら、こんなに效率のいゝ話はない譯だ。
文化的な評判の多くが同業者間のサクラの聲で成つてゐる、そんな馬鹿げた事でも、仕組にしてしまへば、顏形の付いて來るのが面白い。評論家は、批評の荒々しく深い聲を失つた譯知りの業界人に成り下がり、多くの聽衆は、斷乎とした音樂への愛を失つて、唯々諾々たる文化の消費者に成り下がつた。これが文化か、ヴァグナーが聞けば、笑ひ過ぎて失禁し兼ねまい。
さて、今囘、話題となつた映像演出に關しては、殆ど全く論じる必要がない。巨大なスクリーンを背後に掲げて、そこで最新のデジタル映像を寫せば、そこに映つてゐるのが何であれ、要するにオペラは霞み、主役は映像になるに決まつてゐるからだ。映像擔當のヴィオラ氏は、その道では著名な作家らしいが、ヴァグナーに主役を讓り、自分は、背景作りに徹しようとは考へなかつた。無論、この人に仕事を發注した、オペラ座側の魂膽が、そもそも、ヴァグナーのオペラにふさはしい背景ではなく、話題を浚ふやうな「刺激的」な映像を主役に拔擢すること自體にあつたに違ひないのだから、ヴィオラ氏は、お約束の仕事を、ギャランティー相應にこなしたといふ事になるのであらう。これは、藝術家ではなく、見識のない雇はれ人のやる事だが、當節、藝術家の名前をだしにした奴隸根性は、世界に蔓延してゐる、ヴィオラ氏のみにそれ以上を要求するのは、苛斂誅求に近いのであらう。
映像の中身は、豫想を遙かに超えて凡庸だつたが、問題は寧ろ、映像を用ゐたオペラの破壞といふ試み自體の、壓倒的な凡庸さにある。横5m縱10mの巨大スクリーンに、鮮やかな色彩と巨大な形態が寫し出されゝば、その映像が優れてゐようが詰まらなからうが、刺激的だらうが穩健だらうが、結局、これが主役になる。映畫と全く同じ構造、つまり視覺が優先され、聽覺は明らかにその補助に廻らざるを得ない。これは、例へば、人と話をしてゐるところに、やゝ大きなスクリーンでテレビを寫された經驗のある人ならば、すぐに理解してもらへよう。私の目の前に坐つてゐる人が、たとひマリリン・モンローや蝦ちやんで、脇で寫されてゐるテレビが、低級なバラエティーの馬鹿笑ひだつたとしても、どうにも氣移りして、仕方ない筈である。
映像の感覺に與へる強さは、表現の内的な強さではなく、暴力的な感覺への侵入の性格が強い。クラシック音樂の實演は、―演劇と同じく―生身の人間の、いはば肉體的な諸條件の微妙な弱さの克服といふ性格を持つ。舞臺に出て來るのは、我々と同じ等身大の人間で、弱さも醜さも貧弱さも隱しやうがない。その等身大の人間が、リアの科白一つで舞臺に嵐を現出し、ヴァイオリン一つで、宇宙的な沈默の空間を生み出す。それが舞臺藝術の面白さなので、巨大なスクリーンの鮮やかな色彩は、それ自體が、さうした舞臺藝術の微妙さに對しては、單なる暴力裝置としてしか、働きやうがない。カラスやフィッシャー=ディスカウ、フルトヴェングラーやカラヤンならば、このやうな舞臺に出演する事は、間違ひなく拒否しただらう。それは、彼らが、守舊的だからではなく、こゝには、舞臺藝術としての新しさが全くあり得ないからである。
ヴァグナーのオペラのリアリティを支へてゐるのは、その音樂と詩の限りない精妙さである。この精妙さは、聽き手の最大限の注意を要求し、聽き手が、作品の要求する極めて高度な集中力を保持し得た時にだけ、他のどんな藝術や、自然現象からも絶對に受取ることが出來ないやうな、激甚な感銘を與へてくれる。
先日亡くなられた文藝批評家の川村二郎氏は、中學生の頃フルトヴェングラーの『トリスタン』のSP盤を聽いて、高熱を出し數日學校を休んだ經驗を、どこかで書いてをられた。テオドール・アドルノは、やはり子供の頃、フランス人の音樂教師に「フルトヴェングラーの『トリスタン』は是が非でも聽きに行け。君が本當に音樂家になりたいのなら、親の死に目に會へなくても聽くべきなのだ。」と言はれたといふ。無論、私が言ひたいのは、フルトヴェングラーの『トリスタン』の素晴しさではなく、『トリスタン』が、感受性に富んだ子供の生命を脅し、音樂教師に、このやうな、非人間的なまでの激語を吐かせる程、強烈な全身全靈の搖さぶりの體驗たり得る音樂だといふことだ。それが可能なのは、音樂の精妙な言語に、聽き手が徹底して沈潛した時だけなのである。
大スクリーンの映像は、この音樂の精妙さへの、聽き手の沒頭を、致命的に妨げる。腹だたしいのは、そんな事は、始めから分りきつた事なのに、なほ、やつてみなければ氣が濟まない、最近のオペラ演出を巡る、馬鹿者共の、途轍もないあざとさである。實驗精神は結構だが、實驗に値する試みを選ぶ智慧がなければ、たゞの愚行に過ぎない。現代物理學の超紐理論や多元宇宙論は、途方もない思考實驗だし、不毛だといふ聲も根強いが、愚劣ではあるまい。思考上、さうした方向に實驗せざるを得ない聲が、學問の内部から、數多の秀才や天才らの腦裏に囁き掛ける。百の不毛から、一の眞理が燦めき得ると考へるだけの根據はある。
スクリーン映像による演出には、そのやうな緊張した實驗精神はない。第一、そんなに、映像による新しい演出の力を示したいのなら、『トリスタン』などといふ中途半端な素材を選ばぬがいゝ。ヴァグナーに全面的に依存した企畫である點が、まづ、不潔である。シューベルトの『冬の旅』で、巨大なバックスクリーンに、失戀で病附かれた男の心の奧底に蠢く、性交場面を、無修正、音付きで、流してみればいゝだらう。『冬の旅』の内側に病み爛れた「性慾」を發見した、劃期的な演出だと言ひ募ればいゝだらう。どのくらゐ無意味なぶち壞しに過ぎないか、心ある聽き手ならば、強烈な憎惡と輕蔑をはつきり感じる程、生涯の心の傷になるやうな、人生への凌辱の時間となるだらう。やるなら、そこまでやればいゝだらう。『トリスタン』を種に、エロティックな「映像美」で興行を打つなら、金にも話題にも批評の理窟にもなり、傷つく人間はゐない。そんな安直な魂膽に、「藝術」の名前を冠するだけでも汚らはしい。
かういふ馬鹿者共の、論じる必要のない愚行に對して、又いつものやうに、日本の批評は、「理解」を示し、微温的で、どうとでも言へる理窟を竝べるのであらうか。だが、ベートーヴェンも、バルザックも、ヴァグナーも、ニーチェも、マンも、小林秀雄も、チェリビダッケも、三島由紀夫も、―決然たる批評精神の持主をアト・ランダムに竝べただけだ―皆、斷乎たる人間であつた。譯知り顏の微温的な理解などとは、對極にあつた人達であつた。藝術の名の下に行はれる不正には、憤死する程激しく怒ることが出來た。さうした批評精神の緊張感だけが、時代の文化を創出し得る。思ひ付きと實驗精神とは全く別物なのである。
從つて、映像作品としての出來榮えを問題にする必要はないが、私は、型どほりに事を運ぶのを好む人間だから、一言だけ書いておけば、實のところ、純粹に映像作品としても、極めて魅力に乏しかつた。何しろ、始めの航海シーンで、北歐風の暗い海が映し出されるのである。誰もが最初に思ひ付き、最初に捨てるアイディアではなからうか。見てゐて、音樂が運んでくる潮のにほひが、全部消えてしまふ程、氣持が萎えた。
だが、勿論、問題になるのは、―興行主が問題にしてほしいと思つてゐるのは―畫像の中での、トリスタンとイゾルデ役の俳優が、正面を向いて竝びながら、着衣を少しづつ脱いでゆき、終ひに、修正を掛けずに、全裸になる事なのだらう。巨大スクリーンに映し出されたアポロならぬ中年フランス男の萎縮氣味のペニスなどといふ、世にも見たくない代物を見せてもらつた。4萬2千圓支拂つただけの事はあつたのである。だが、これは、日本の法律に明白に引つかかるのではないのか。主催のフジテレビの重役どもを、豚箱にぶちこまなくていゝのか。こゝはそれ、「お藝術」とやらだから、許されるといふ譯か。秋葉原で股を廣げて寫眞を取らせてゐた女の子は逮捕されても、傳統あるオペラハウスの引越公演の大畫像で、男女の恥部を丸出しにするのは、立派な藝術といふ譯か。
どうせなら、あの場面で、會場の全員に呼び掛け、起立させ、皆でズボンとスカートと下着を一齊にずり下し、同胞同士の陰部をつくづく鑑賞しながら、『トリスタン』の官能性に深く思ひを致すやうな、會場參加型で平等主義的な『トリスタン』演出でもすれば、話題は世界的なものになつたであらう。演出が、そこまでの英斷を下さなかつた事は、まことに殘念だつた。私の兩隣には素晴しく美しい女性が坐つてゐたのだから、尚更惜しい氣持が殘る。次は、是非、そこまで徹底した企畫で、トリスタンの官能を徹底化することを、オペラ座總裁殿には愼んで提案しておかう。
さて、お定まりに話題にすべき“衝撃全裸映像”はこれで片付いたが、後は、取上げる程の箇所はない。特に、センスがないと思はれたのは、3幕、トリスタンの長い獨白の場面であらうか。『生き物地球紀行』風の、平凡な自然の、風景描寫で、川のせせらぎや林などが映されて、この内面的な痛苦のドラマは、まるで、畫像にからかはれてゐるやうであつた。何を考へてゐるのか、時間がなかつたのか、豫算がなかつたのか、才能がなかつたのか、テノール歌手に恨みでもあつたのか。「愛の死」の場面で、トリスタンの遺體が海中から上昇し、空に飛び出してゆくといふのは、とつておきのアイディアだつたのかもしれないが、生々し過ぎて遣りきれない。土左衞門が水に浮く聯想をしてしまふ。餘りのことに失笑していゝのか、感動していゝのか、分らなくなり、混亂の餘り、私はつひにおならがしたくなつたのである。もし、私が、尻の穴の緩い人間だつたなら、兩脇の美女らは、どういふ目にあつた事であらうか。彼女らの鼻腔を衝く不快な臭氣の責任は、一體誰が取るべきといふ事になるのか。(この項續く)

