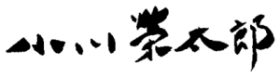パリ國立オペラ引越公演『トリスタンとイゾルデ』7月31日オーチャードホール(2)(2008年8月6日)
(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2008年08月06日より)
昨日掲載した後で、知人から、他のブログで熱烈な贊辭が散見されると教へられた。それはそれでいゝし、他の人の感動に水を差すつもりはない。だが、それでも、私は言はなければならない。
昔、面白い男がゐた。やゝ小太りのお人好しで、音樂好きな、商家の旦那風の男だつた。小心者だが、惡黨ではない。人に小馬鹿にされても、氣にしない鷹揚さもある。長く話してゐると、やゝ癇癖のある私は、苛々してくる。どこまでも芒洋としてゐて、話にまるで彈みがつかないからだ。暖簾に腕押しといふが、どちらかといふと、ゴム鞠のやうな男だつた。それだけに、遠慮もない。芒洋としてゐても、一向に議論は讓らない。そこが、面白かつた。
この男は、北歐の音樂が好きで、若き日のサロネンやヤンソンスをいつも襃めそやしてゐた。「水のやうに凡庸で、とても聽く氣がしないね。」私は苦り切つて、斷言する。聽く氣がしないのだから、實際に聽いてもゐないのである。斷言するのは、その男の面が氣に入らない、脂下つた面で襃めそやすのが、いけすかない、まあそんな處であつたらう。相手も負けてはゐない。どんなに否定されても、平氣の平左である。彼には彼の武器がある。二言目には、「あんたの好きなフルトヴェングラー、あれは單なる演歌だら。ヤンソンスの方がよつぽどセンスがいゝら。」と來る。(東海地方の人だつたのである。)「何が演歌だ。フルトヴェングラーの演奏は、和聲的な構造の次元を開示してゐるので、その歌謠性の析出される基盤が、單に感情耽溺型の演奏とは違ふのだ、云々かんぬん。」無論相手はへこまない。にやにや笑ひながら、「理窟はどうでも、やはりあれは演歌だら。」
要するに、私が、どんなに否定しようが、今囘の《トリスタン》に、疑ひやうのない感銘を受けた人がゐれば、その人は、己の感銘を守ればいゝ。感銘の經驗こそが羅針盤である。感銘がなかつた場合の批評や判斷には、必ず恣意が働く。あらゆる種類の否定の情熱から、恣意を取り除き、適切な判斷のみを殘すことは、極めて困難な事だが、それでも、人は、斷乎として否定の發言を貫かねばならない場合があるのである。
さて、パリ國立オペラ、モルティエ總裁の會見記事を昨日の投稿の後讀んだが、《トリスタン》の映像には、3億圓が掛かつてゐて、これはオペラの演出費用としては空前のものださうである。魂消たとはこのことだ、それならば、公演代金の多くをあの映像に支拂つた譯か。
昨日書いたことを改めて確認するつもりはない。だが、映像によつてヴァグナーの微妙な味はひが全て死ぬといふのがおまへの主張であるにせよ、しかし、その上で、演出が主題に對して果してゐる役割は論評すべきなのではないか、つまり、エロスの問題にどう取り組んでゐるかといふ、演出上の眼目におまへは全く觸れてゐないではないかといふ讀者があるかもしれない。
それには簡單に答へられる。《トリスタン》のエロスは、極めて抽象化されたエロスである。別の言ひ方をすれば交響化されたエロスである。あそこには、エロスと權力といふ主題を始め、樣々な讀みを誘ふ仕掛があるやうに見えるが、實際に作品の傳へる感銘は、性愛や樣々な權力論とは全く關はらない、音樂的なフォームによるものだ。あへて言へば、この作品は、セックスなぞ詰まらないと言つてゐる。作品には、男を欲する女も、女を欲する男も出て來はしない。もし性愛が主題であるならば、媚藥によつて一瞬で燃え上がるなどといふ設定に意味はなくなる。心理的な過程のない性愛とは、純然たるポルノだからだ。だが、この作品の感銘は、明らかにポルノ的なそれとは別の領域のものである。それは、ヴァグナーに關してよく言はれる靈と肉との相剋とも違ふ。こゝには、始めから肉體の要素が殆どない。性愛といふよりは靈的な一體感が、媚藥によつて、始めの瞬間に成就し、後は、全作品、その事の意味を確かめ手應へを深め續けてゐるだけである。《パルジファル》とはポジとネガの關係、だが、その純粹性は、同じ水準にある。ヴァグナーは、この作品に「舞臺神聖劇」と名附けても、良かつたのである。
演出が、人間の肉體を感じさせた段階で、この作品の核心部分が失はれる。フラグスタートの、まるで天のお告げのやうな聲(フルトヴェングラー盤)と、ヒーリングヴォイスの先驅けのやうな透明なマーガレット・プライスの聲(クライバー盤)は、どちらも、「女」の肉體を感じさせることから最も隔つてゐる。昨秋のバレンボイムの時のヴァルトラウト・マイアーは、風貌も聲も、巫女そのものであつた。これらは、性の隱蔽ではない。《トリスタン》は、性の極端な抽象化によつて成立してゐるので、それを、生臭い體臭にまで逆行させるのは、作品の精讀でも讀み換へでもなく、破壞に過ぎないといふだけの話である。
音樂面では、昨日書いたやうに歌手の健鬪は充分評價するものゝ、特に感銘深くはなかつた。
まづオケがヴァグナーにはそぐはない。洗練されてゐるが、餘りにも厚みがない。肝心なところで踏ん張りが利かない。無論、彼らフランス人に言はせれば、さういふ野暮をやりたくないと言ふかもしれないが、野暮なまでに唸つて啖呵を切らなければ、ヴァグナーではないだらう。もつとも、これはフランス人のやるヴァグナーの拒絶ではない。彼らはそれを貫き、私は惡口を言ひ續ける、蓼食ふ蟲も、といふ奴で、これが文化の「構造」といふものだ。ヴァグナーをやつても自國流儀を貫く彼らの自己主張の強さ自體は嫌ひではないのである。
指揮者のビシュコフも、才能ある人と感じたが、音樂のとらへ方が、これ又徹底してアンチドラマで、ペレアス風にレガーティッシモな演奏である。オケの性質を輪にかけてスタティックな音樂へと傾斜しがちで、これは、私の我慢の限界を超える。第1幕への前奏曲から、厭な豫感がした。この音樂の中に無數に編み込まれた精妙なドラマが、全て地ならしされて優しい風のそよぎになつてしまつてゐる。あへて探し出して、指揮で印象に殘つた箇所を言へば、2幕の後半、愛の2重唱の丹念で靜謐な緊張感から、マルケ王の場面であらうか。こゝは、音樂に沈潛し、理解も深い上演だつたやうに思ふ。全曲で最も抒情的な場面だつた爲だらう。
そんな中、健鬪してゐたのは歌手陣である。
イゾルデは聲は質量ともに立派だが、かと言つて決定的な魅力があるといふ程でもない。ブランゲーネとの最初のシーンで、音樂の讀みの細かさや、巧みにドラマを作つてゆく力は、昨秋のマイヤー=バレンボイムとは、桁が一つも二つも違ふ。正直なところ、いゝ演奏では、既にこの邊りから、無我夢中になるのに、私は、耐へざる眠氣に惱まされとほしだつた。だが、通して聽くと、二幕のトリスタンとの掛合ひも、「愛の死」も堂々たる歌ひ振りで、これは歌手として充分立派な仕事振りだと言ふべきだらう。
だが、歌手の中で、私の耳を特にはつきりととらへたのは、クルヴェナール役のダニエルである。深く威嚴のある聲で印象に殘る、場合によつて、トリスタンよりも前に出る感さへあつた。フォービスによるトリスタンは高音に限界があるとは言へ、緊張に滿ちた力強い歌で、決して惡い出來ではない。たゞこゝまでは、昨年のベルリン國立歌劇場の奇跡のやうな上演とは、匹敵し得ない。指揮の統率力が違ふことで、歌手が、實力以上に役柄にのめり込めるかどうかが決まる。バレンボイムとビシュコフの實力差が、結局、歌手たちから來る音樂的なオーラの飛散の度合を決めたのであらう。全體として、あの時以上に感銘深かつたのはマルケ王のセリグで、傷ついた王の悲しみは深々と迫つてきた。
さういふ意味で、歌手が優秀であつたからこそ、改めて《トリスタン》が、徹底的に指揮の藝術であることを再認識させられた上演であつた。ハンス・フォン・ビューロウが、初演に漕ぎ着ける爲に繰返したプローベは200囘を下らなかつたと思ふが、それは、この曲が1850年代としては、桁外れの難曲だつたといふ理由だけではない。正に、作曲者ヴァグナーと指揮者ビューロウの協同事業として《トリスタン》は誕生したのである。そして、また、この《トリスタン》の上演を通じて、事實上、近代指揮藝術は、誕生した。《トリスタン》に徹底的に鍛へられたビューロウの指揮の技術が、後にブラームスの理想的な解釋者に、彼を仕立てたからだ。
その後、《トリスタン》は、マーラー、R・シュトラウス、トスカニーニ、フルトヴェングラー、カラヤン、クライバー、バレンボイム、ティーレマンと、指揮藝術のチャンピオン達の、王位證明の核心的な演目であり續けた。演奏への批評の聲が微弱になつてゐる今日、改めて主要な《トリスタン》レコーディングを素材に、徹底した《トリスタン》の作品論=演奏論に取り組む價値はあるのかもしれない。(この項了)