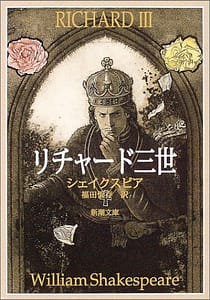#2 『リチャード三世』
暫くシェイクスピアを集中してご紹介する。
文学を身に付けるには、一人の作家を纏めて読む事が絶対に必要である。様々な作者の代表作と言はれるものを広く浅く読んでゐては、読書リストの名簿が増えるだけで、作家の言葉の力も人間観も、その天才から放射されるアウラも何も身に付けられずに終はるだけだ。
考へてもごらんなさい、人間づきあひでもさうでせう。
その道の優れた人物に会つてみようといつても、1時間の面会を五十人の人間に対して次々に重ねたところで、面会有名人リストが増えるだけで、人間としての何かを身に付けた事にはなるまい。「あの人はさすがにオーラが凄い」などといふ言ひ方をする人がよくあるが、殆どの場合錯覚に過ぎない。人が放つアウラの素晴らしさは、社会的に大物かどうかとは関係ない。無名の人の中にもアウラの素晴らしい人は沢山ゐる。著名かどうかなどどうでもいい、そんな不確かなアウラを浴びて喜ぶよりも、人としての彼の体臭が――良し悪しいづれも含め――感じられる位まで付き合ひを深める方が遥かに面白からう。
「人間を知る」といふ事以上に、人生に面白い事があるか、さういふ情念に動かされたのが古来の優れた文学者である。彼らが人間を深く知るその知り方の秘密を覗かねば、さうした大作家と付き合ふ甲斐がない。生涯の友を作るやうなつもりで文学者と向き合ふ事。現代の有名人と名刺交換するよりも安上がりで比較にならぬ富を得る事ができる。ところが、殆どの人が、あなたの目の前で待つてゐてくれる人類史上至高の友人たちの前を素通りし、安物の前に人だ
かりがしてゐる始末だ。憐れむべし。
*
前置きはここまで、シェイクスピア初期作品からは、『リチャード3世』を御勧めしておかう。
シェイクスピアの作品は、処女作から最後の『テンペスト』まで全て面白い。全く退屈せずに全集を通読できる作家は大作家にも多くはないが、シェイクスピアはその筆頭であらう。
26才で書かれた処女作『ヘンリー6世』は、壮大で複雑極まる歴史劇だが、既にレーゼドラマとして読んで抜群に面白い。多くの学者は26歳の若者がいきなりこんな芝居を破綻なく書けたかと疑義を呈し、先輩作家たちとの合作を想像してゐる。エリザベス朝時代は演劇の華やかだつた時代で、シェイクスピアの周囲には人気作者が覇を競つてゐたからだ。が、私は信じない。シェイクスピアと同い年だが仕事がやや先行するクリストファー・マーロウにせよ、トマス・キッドにせよ、代表作とされる仕事でもシェイクスピアとは水準が違ひ過ぎる。私はだいぶ以前、筑摩書房の『エリザベス朝演劇集』(小津次郎、小田島雄志編)を通読した事があるが、当時の代表作を集めたこの分厚い一冊の中に、『ヘンリー6世』の足元にある作品さへなかつたといふのが正直な感想だ。25歳のゲーテがいきなり『若きウェルテルの悩み』を書き、29才のワーグナーが『さまよえるオランダ人』を書き、19才のランボオが『地獄の季節』を書いたやうに、シェイクスピアも26才で『ヘンリー6世』の高みにいきなり到達して、何か不都合があるだらうか。
十人の経験豊富な秀才作家がいかに巧みに協働しても、一人の天才の代りを務める事は出来ない。
この一〇〇選では、初期シェイクスピアの中から『リチャード三世』を御勧めしておかう。冷酷無慙な謀略で兄弟や身内を次々に殺し、権力の座に辿り着いたグロスター。が、王権を奪取し、リチャード3世を名乗つた瞬間から、彼の破滅は始まる。王座を射止めるまで謀略を支へたバッキンガム公をさへも切り捨て、あらゆる味方を裏切つた報いとして、彼は戦場に散る。権力獲得と破滅をこれ以上ない鋭い対象として描くこの作品は、四大悲劇のやうな内面劇ではない。が、政治スペクタクルでありながら、人物造形の抉りが徹底的で、畳みかけるやうな謀略劇の数々が、人間性の深淵をこの上ない鮮やかさで照らし出す。
我が日本の文学は、裏切られてゆく者たちの悲しみは――シェイクスピア以上の筆力で――描けるが、リチャード三世のやうな徹底的な悪党を描く事はできなかつた。それだけの悪党がゐなかつたといふ訳ではないだらう。雄略、天智、天武のやうな古代天皇、蘇我入鹿ら蘇我一族、道鏡、平将門、平清盛、源頼朝、足利義満……。が、彼らを辛辣さの側から抉り出す文学は日本の古典にはない。人麻呂、家持、紫式部はゐても、『史記』やシェイクスピアに匹敵する悪のバイブルは我が国ではつひに書かれずに今日に至つてゐる。これはわが民族の長所か、それとも負ひ目なのか。
いはば悪漢ロマンの先蹤として、『リチャード3世』は、以後のヨーロッパ藝術に対する典型であり続けた。『ドン・ジョヴァンニ』、『ファウスト』、『悪霊』、『詐欺師フィリップス・クルルの告白』……。その悪の沃野は豊かな裾の拡がりを見せるが、しかしグロスターのやうな簡勁極まる悪の野太い立ち姿は、それら近代の悪漢たちからは失はれたやうである。心理主義的リアリズムはつひに悪を悪として描けない。ジョヴァンニはグロスターと違ひ女を本当に愛しつつ彼女らを犯す。ファウストにはメフィストが、スタヴローギンには革命の幻想が必要だつた。無論、詐欺師にまで身を落とせば、それは既にグロスターとは無限に遠い存在でしかない……。
グロスター やつと忍苦の冬も去り、このとほり天日もヨークの味方、あたり一面、
夏の気に溢れてゐる。一族のうへに低く垂れこめてゐた暗雲も、今は海の底ふかく追
ひやられてしまつた。頭上には勝利の花輪が輝き、傷だらけの物の具は誇らしげに思
ひ出を語り、けたたましい軍鼓の響きは楽しい宴に、苦しい進軍の足取りは軽やかな
踊りに代つた。(福田恆存訳)
作品冒頭である。芝居といふものも、タイトルロールのこんな前口上で始まる事が出来るのである、一人の天才がゐさへすれば。総製作費数百億円のあぶく銭で下手な効果を狙ふ映画を撮る暇があれば、人類は天才を生む文化を大事にした方がよほどいい。安上がりな上、本当に末代までの尽きせぬ富となるのだから。