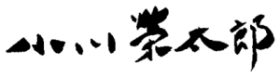バッハ《平均律クラヴィーア曲集第1卷》byダニエル・バレンボイム(6) 小川榮太郎(2008年03月27日)
.jpg)
(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2008年03月27日より)
バレンボイムは、當然ながら、昨日書いたグールドとは、まるで別の道をゆく。彼は、傳統に從つて、冥想的なマエストーゾで、この曲を彈き始める。しかし、彼がこの音樂から取り出したダイナミズムは、音量としても、音樂的な緊張としても、例のない大きさに達してゐる。グールドの後に聽くと、バレンボイムのバッハの味の濃さには驚かされる。蘊蓄を傾けて、バッハの音樂言語の可能性を縱横無盡に語り盡さうとする趣は、比較を絶して壓卷であつた。
このやうな晦澁なフーガの演奏を言葉で追ふのは、無意味なやうだが、一應、杓子定規なノートをとつておく。
押し殺したやうなピアニッシモで始まるフーガの主題は、苦惱を負つた者のモノローグのやうだ。すぐに2聲、そして3聲になると、それが、寧ろ、扇が開くやうに、樣々に異なつた物語の祕密を明かし始める。聲部の遠近法は、明確だ。音樂は聲部を増すにつれ、遲いテンポのまゝ、ダイナミズムを擴大し始めるが、特に、36小節で、第2對主題が8分音符で出る邊りからは、それまでの抑制から放たれ、音樂は雄大な歌にうねり始める。49小節の第1對主題は、哀切なフォルテで現れる。この主題は、後半の音樂を主導するのだが、この印象的な出は、バレンボイムの演奏では、後半が滾々と溢れるクレッシェンドの山脈になる事の、豫告ともなつてゐる。
73小節で、フーガ主題の低音が、バスに再歸するところでは、このバスがオルガンのやうに朗々と響き、それを足場に、いよいよ多聲的な展開は緊迫し、92小節にソプラノに現れる第1對主題で、いはば絶唱となる。この邊りになると、フーガ的な明晰がいさゝかも犧牲にならないまゝ、音樂は殆ど大地の鳴動するやうな巨大なフォルテのうねりに包まれてゐるのは、驚きである。
音樂的な内實はまるで別だが、バレンボイムの奏するこのフーガは、《ボレロ》のやうに、ピアニッシモからフォルティッシモに漸強を續ける一つの巨大なアーチなのである。その事が、はつきり聽き手の耳にもこゝろにも屆くのは、やはり曲の終結部だらう。この曲は、屬音のオルガン・ポイントに入るのが105小節で、曲がをはるのが115小節なのだから、終止部分もずゐぶん念入りに作られてゐるのだが、バレンボイムは、この105小節で大きな山を作つて、その後緊張のアーチを大きく保つたまゝ、112小節で主音に入る瞬間に、最大のクライマックスを置く。だが、こゝには、對主題の旋律も又、殘つてゐる。フォルティッシモで奏すれば、耳を聾する不協和音になるのである。バレンボイムはそれを敢行する。つまり、彼の演奏では、主音への解決に入つたその音が、同時に、恰も、大きなカタストローフのやうに響く事になる譯だ。そして、そのカタストローフの破片が、右ペダルの持續の中から徐々に消え去ると、主音のやはらかい終結の表情が導かれ、曲は、悲劇の後の聖なる平穩としてをはるのである。
5聲のフーガが織りなす巨大な山竝と劇的なカタストローフ、そして、その後に導かれる滿たされた終結の調和――これは、傳統的な、或いはピアニスティックな、「舊スタイル」のバッハなどと云へるものなのだらうか?
この曲の全曲盤は、私の知る限り1930年代のエトヴィン・フィッシャー(寫眞)のものが最初だが、そもそもそれ以前のこの曲は、學習用、或いは作曲家のインスピレーションの源として、主に音樂家のプライベートルームで研究され、彈かれてゐたので、演奏會レパートリーではなかつた。そして、フィッシャーは、事このバッハに關しては、新古典主義的な演奏を展開してゐる。往時の名著、野村あらえびすの『名曲名盤』(中公文庫)で、「アカデミックで幾分學者風」と評されてゐるやうに、この演奏は、當時の聽き手にも、さほど面白い自由なものとは聽こえなかつたのである。生演奏のフィッシャーが、フルトヴェングラーとのブラームスのコンチェルトでの、濃厚なロマンや、モーツァルトの彈き振りでの、自由から爛熟に近づくかと思はれる奔放な歌で沸騰してゐたことを思へば、アカデミックなバッハが、フィッシャーといふ音樂家の地ではなく、歴史主義的なバッハ像への“遠慮”の産物であつたことは、想像に難くない。
そして、このフィッシャーの後、バレンボイムの演奏のやうに、和聲音樂としてのバッハの音樂に内在する和聲的なエネルギー量を、古樂的な知見を振り切つて、こんなにも直截に表現するところまで大膽なバッハ演奏は、少くとも私は寡聞にして知らない。つまり、バッハ演奏の傳統の中には、このやうなバッハは、實はありさうで、全く存在してゐなかつたのではあるまいか。そして、これは、指揮者としてヴァグナー、ブルックナーに精通してゐる人が、バッハの音樂に内在する表出力を、後の西洋音樂の達成の側から讀み切つてみたといふ意味で、フィッシャー、グールドから古樂に至る、アンチ19世紀としてのバッハ傳統への、積極的な叛逆ではあるまいか。
餘りにも忙しい時代、批評が新譜の手早な論評に忙しく、熟考と論戰が消えてしまつてゐるのは、殘念である。多數のレコードを一瀉千里に“鑑定”するのも、今日では意味を持つのは確かなことだ。『レコード芸術』の「何でも鑑定團」や、『クラシックジャーナル』の膨大な新譜批評などは、重寶だし、時に樂しみでもある。しかし、一方で、里程標になるやうな音樂家やレコードを、音樂的な意味として充分に考察する習慣が全く消えてしまつたことを、當然としていゝものだとは、私は考へない。例へば、このバレンボイムのバッハ演奏のやうに、20世紀のバッハ演奏史全てに對する本質的な批判を含みながら、實現された美の峰高いものは、通り一遍の批評で右から左にやつつけられていゝ筈はないのである。
私の家は陋屋なのだが、5分も歩くと、海を一望出來る宏壯な別莊地が廣がつてゐて、毎朝、春の息吹を感じに散歩に出るのが、さゝやかな樂しみになつてゐる。さすがに別莊地の家々の、家竝は豐かに整ひ、庭の美も行き屆いて、餘所の家ながら、その庭の木々花花に、日毎春が濃くなるのを目に確かめる樂しさは、格別である。今日は、紅白のコブシを配した庭に、梅とは違ふ豪奢な色彩の對照を發見して、悦に入つてゐる。さう思へば、良い庭を丹精するのも、大きく云へば布施行であり功徳なのでもあらうか。
ちよつとした空き地にまで、菜の花が咲き誇り、耀くばかりの黄で目を射る。その横には健康な卵黄のやうな濃い黄の蓮行が、いゝ枝振りである。少し林が深ければ、枯葉をかさかさ云はせながら、うづらがゑさを探してゐる姿が見え隱れしてゐる。
我が家の側を通る櫻竝木では、櫻の蕾が、膨らみ、枝がその重みで赤々と、枝垂れ始めた。生命の燭の耀かな豫告である。が、それを更に降りた城ヶ崎海岸ではすつかり開花した櫻さへあるのである。これには驚いた、うろうろストーブさへ付けてゐる私を置いて、春の音づれは私を出拔くのだらうか……下手な『枕草子』で、恐縮だ。明日からは、出來れば暫く、1囘讀切を目指して、マーラーやショスタコーヴィチのレコードを何枚か扱はうと思つてゐる。(この項了)