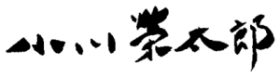ダニエル・バレンボイム指揮ミラノ・スカラ座管弦樂團&合唱團/ヴェルディ《レクイエム》(2009年09月13日)
(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2009年09月13日より)
バルバラ・フラットリ(S)エカテリーナ・グバノワ(M)ヨハン・ボータ(T)ルネ・パーペ(B) 平成21年9月10日 於NHKホール
バレンボイム指揮のスカラ座を聽く事になるとは、少し前まで思ひもしなかつた。バレンボイムファンの私にとつては、ムーティの突然の辭任による嬉しい誤算だが、イタリアオペラのファン達がどう感じてゐるのかは、又別の話になるだらう。《アイーダ》は明日の最終公演を聽く豫定なので、それに先立つての、今宵の《レクイエム》だつた。この度の、スカラ座來日公演は、この二演目以外に、ダニエル・ガッティの《ドン・カルロ》が含まれるから、六十歳前後のヴェルディ最盛期の重厚な傑作を纏めて取上げるといふ企畫である譯だらう。《アイーダ》と《レクイエム》は、初演時の歌手さへ共通してゐたといふ。スカラ座の來日公演のプログラムとして、充分興味深い取り合せである。
今日のバレンボイムの指揮は、期待程ではない。前囘の來日時のオーケストラ公演もさうだつたが、全力投球のオペラに較べると、やゝ流した所のある演奏である。音樂への共感がさほどでもないのか、スカラ座のオーケストラに對しても、限界までの力の發揮を求めてゐるやうには感じられないのは、偶々なのか。アンサンブルの自發性を求めて、縱の線をあわせないのが、この人の最近の專らだが、今日の演奏では、このやり方は、奏效してゐない。ヴェルディでは、やはり、線の明晰さ、オーケストラの音彩を注意深くブレンドする事が必要だらう。スカラ座での《トリスタン》のDVDは素晴しかつたから、《アイーダ》には期待したいが、バレンボイムがスカラ座管弦樂團を、まだ、掌握しきれてゐないといふ印象がある。
しかし、無論、現在のバレンボイムが振れば、何と言つても、非凡で豐かな世界が展開されてゐた事だけは間違ひない。
冒頭のレクイエムとキリエが或いは最も素晴しかつたであらうか。靜謐なチェロに乘つて、合唱が深い憧憬と懇願の限りを盡くす吐息のやうな開始には、息を飮んだ。感傷的ではなく、宗教的な沒頭がある。キリエも、トスカニーニの場合に極端にさうなるやうな凱旋行進のやうではなく、内省的で、グレゴリオ聖歌に由來する靜謐さ注意深く取り出される。チェリビダッケの素晴しいCDを思ひ出した。このまゝ行けば、劃期的な演奏になるかと思はせたが、これ程の高みは、この後聽けなかつたのが、殘念である。
怒りの日になると、バレンボイムが、オーケストラを、嚴格な緊張の高まりに導かず、響きも期待したより薄手である。合唱のマッシヴな力はさすがで、これは期待通りだが、それにも關はらず、後一歩、何か、途方もない瞬間が生じる時の、あのバレンボイムとは、明らかに違ふ。
歌手では、トゥーバ・ミルムを始めとする幾つかのシーンでのルネ・パーペの極めて内面的な歌唱は印象的だつた。歌唱と言ふよりも、場合によつて演唱と言ひたくなる程、演劇的で、しかも、レクイエムの内容から逸脱してゐない。前囘、バレンボイムと共に來日した時のマルケ王でのパーペが、まるで勝者の凱旋のやうな歌ひ振りで私を立腹させたのを忘れさせる名唱である。
フラットリを始め、他の歌手も、さすがに見事な歌ひ振りで、その點には不滿はない。だが、全體が充分に統合されたといふ印象は希薄である。指揮者と共演者の間で、充分に音樂内容を詰めた上での上演とは、率直に言つて感じられない。獨唱や重唱の質の高さとは別に、音樂作品全體に、充分に練られたアンサンブルの氣配がない。
演奏は、細部に渡り、デクレッシェンドの息を飲むやうな靜寂や、オーケストラパートの息の長いフレージング、また、伴奏を超えたオーケストラの表現への參加が、絶えず、得點を重ねてゐたのは事實である。その意味では、非凡な演奏ではあつたのである。しかし、音樂の感銘は、個々の得點を超えた一貫性や一體感による、緊張と燃燒にある筈だらう。それは、誰よりもバレンボイムが解つてゐる筈だらう。
ラクリモーザは、如何にも楷書でしつかりと演奏されたが、胸を付くやうな、取返しの付かない悔悟感はなく、やゝ立派過ぎようか。サンクストゥスと終曲の壯麗な合唱フーガは、テンポが早過ぎる。いや、速い分には構はないが、合唱が充分に發聲し切れず、上滑りしてゐる。冒頭を始め、音樂が沈潛する幾かの場面では、演劇的なまでに言葉を大切にしてゐるのだから、このやうな聽かせどころは、もつと大切にしてもらひたいものだ。
バレンボイムは、自分の感興が、本當に高まらない時には、舞臺上演上の必要から大向うを唸らせる見得を決して切らない。これはこれで見識だとは思ふが、舞臺藝人である以上、さうしたけれんみは時に欲しい。テーリヒェンの『フルトヴェングラーかカラヤンか』によると、カラヤンは地方公演では、最後の五分だけ本氣になつてオーケストラを煽るやうな事もあつたらしい。テーリヒェンはこの本を書いた頃、アンチ・カラヤン派だつたから、かういふ話に、幾分惡意ある誇張がなかつたかといふ疑念は殘るにせよ、あつてもをかしくない話である。對照的に、どんな地方公演のライヴ録音を聽いても、壯絶なまでに、100%の直球勝負をしてゐたのはフルトヴェングラーだが、彼は六十八歳で死んでしまつた。長生きも藝の内であるとすれば、バレンボイムにも、カラヤン流儀の老獪さを、時に求めたくなる。
惡口を書いたが、どこを取つても、音樂に横溢した素晴しい時間だつた事は、付け加へておきたい。私は、バレンボイムのオペラやベートーヴェン、シューマン、ブルックナーの交響曲、ベートーヴェンのピアノソナタやバッハの平均律で、何度となく、偉大な演奏を聽いてきた。この人が、時に、肩に力を入れずに、日常的な演奏で流す事が往々あるのを知つてゐても、やはり、あの偉大としか言ひやうのない、一期一會を求めたくなるのである。(まして、スカラ座とのヴェルディ《レクイエム》である!)
終曲は、結構布陣の壯麗な演奏で、フラットリの極めつきの美聲も、宗教的な淨化の表情へと深まり、後ろ髮引かれるやうな感銘を殘してゐた。
宗教的な敬虔さへの疑義が言はれるこの曲だが、それは、やゝ新教的で窮屈な見解と言ふべきだらう。カトリック系の宗教畫の、色彩と演劇性に畫家自身が恍惚となつてゐるやうな作品の數々を見れば、ルネッサンス以後、劇的で、豐麗で、信仰の劇的樣相自體を客觀的に敍する姿勢は、イタリアの宗教表現の典型と云つてもいゝ筈なのである。そして、又、このオペラ性と宗教的な眞摯さとの折合を、どう付けるかといふ挑戰には、誰一人滿足のゆく答へを出してゐない。冒頭のレクイエムの素晴しさが、最後まで持續するやうなバレンボイムならではの全曲演奏を、いづれ、期待したいと思ふ。(この項了)