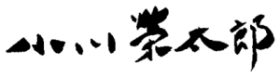ダニエル・バレンボイム指揮/ベルリンシュターツカペレ管弦樂團/シューマン交響曲全集を聽く(3)(2009年11月26日)
(旧ブログ「ザ・クラシック評論」2009年11月26日より)
(承前)シューマン作曲交響曲第1番1樂章の演奏比較(オットー・クレンペラー、レナード・バーンスタイン、ダニエル・バレンボイム)
ヤンソンスの演奏會批評が入り、その後、文藝批評の執筆にをはれてゐた爲に、この稿が、そのまゝになつてゐた。何とか、全4曲の詳細な批評を、たとひ讀者には退屈でも書いておかうと思つてゐたのだが、殘念ながら、此度は、1番の1樂章のみで、中止する。ティーレマンのバイロイトライヴの《指環》全曲盤が間もなく發賣されるので、それを機に、數ヵ月掛けて、《指環》に關する多少纏まつた評論作品を書かうと思ひたつたからだ。竝行して稿を繼ぐだけの時間はない。
そこで、ここに、この度、バレンボイムのシューマン全集を通して熟聽した印象だけは簡単に書いておく。一言で言へば、これは、私の聞いた、最高最良のシューマンの交響曲全集だといふことだ。1番は、一聽地味だが、シューマンの憂愁、そしてシンフォニックな大きさを、4樂章の後半に向けて解き放つ、柄の大きな演奏である。それでゐて、ゆらぐやうな波打つ和聲感は豐かで、かみ締める程に味はひ深い。2番は、生氣溢れる、堂々たる、本格交響曲としての演奏だ。バーンスタインや、それ以上のスケール感のあるティーレマンのやうな飛拔けた大きさはないが、等身大のシューマンは、どこまでも晴朗である。3番《ライン》は、驚く程生氣溢れ、一氣呵成の奔流である。大膽なティンパニが轟き、テンポも大きく搖れ、全曲にわたつて、歡喜が迸る。絶えず前進する波浪のやうに、音樂はうねりながら、山のやうに盛上がる。それでゐて、中間樂章の味はひも、又、濃厚である。郷愁にかられる。これ程、夢中になつて全曲を通して聽いた《ライン》は、私には初めてである。4番は、サントリーホールでの生演奏に、大變感動した曲だが、レコードも大變いゝ。生演奏の時は、1樂章の展開部邊りで、音樂がたゆたふ時の、和聲感の見事さ、もうオーロラがホールをつゝむやうな變化自在な色彩の海に、私は夢中で溺れたものだ。レコードでは、さすがにあの感じまでは出てゐない。しかし、全體に低徊しないテンポで、こゝまでシューマンのロマンティシズム、歌を、生命力いつぱいの發露として、表現して、しかも、それがどこまでも深みのある内省に支へられてゐるのは、見事といふ他ない。2樂章の侘しい晩鐘のやうなえも言はれぬ色合ひ、3樂章から4樂章への緊張に滿ちたブリッヂ、そして、奔流のやうに溢れる4樂章、コーダの天に駈け上がるやうな昂揚――。
餘興で、順番を付ければ。
第1番では、1位:バレンボイム。2位:クレンペラー。3位:バーンスタイン。
第2番では、1位:ティーレマン。2位:チェリビダッケ。3位:セル(ライヴ)。
第3番では、1位:バレンボイム。2位:チェリビダッケ。3位:シューリヒト。
第4番では、1位:フルトヴェングラー。2位:バレンボイム。3位:カラヤン=ヴィーンフィル。
さて、約束の一端だけでも果す爲に、シューマンの第1番の1樂章に就てだけは、詳細に書いておく事にしよう。
1樂章冒頭のファンファーレはさすがに、3巨匠いづれも堂々たるものである。だが、金管がフォルテで出た後、トゥッティのffで繰り返される時の、呼吸の深さは、バレンボイムが一頭地抜いてゐる。注意深く聴いてゐると、バレンボイムでは、音を出すといふ意識の前に、呼吸が先行し、呼吸が音樂を導くといふ氣配がある。そして、實にこまやかなダイナミズム。金管のファンファーレが下降音型で、和聲的にも不安定であることを明瞭に示すやうに、デュミニエンドし、晴れやかさの中に、實は、憂鬱な氣配がこもつてゐることを示すと、それに呼應するトゥッティは、後半に向けてクレッシェンドする。始めの4小節が、凹型の孤をなしてゐる。呼吸するやうな自然なダイナミズムに聞こえるが、實は、音樂的に、大變理にかなつてゐる。そして、このやうなファンファーレの中に眠つてゐる、ダイナミズムを構造化する事で、このファンファーレは、《運命》の冒頭のやうに、全曲を導く一つのモットーに聽こえる。彼の演奏の、最近のスケール感をささへてゐるのは、實は、音樂の細部を、呼吸のやうに自由に扱ひながら、和聲的な論理を通じて、全曲を再構成してゐる事から來る、全體感である。クナッパーツブッシュのやうな、音の存在感で、音樂の大きさを出す、まあ時にあの行き方もいゝけれど、一面、單調で、知的な手應へに缺ける。クナの音樂との係はり方は、私は好ましいと思つてゐるが、日本の一部批評家のやうなクナ禮讚は、滑稽だと、前々から思つてゐる。異樣に誇張され、音樂的知性を缺いた賞讚は、かへつて、彼の音樂の、あの大地にずんと根を下した自然な藝風への、ファンらの、自然な接し方を妨げてゐるやうな氣がしてならない。
無論、バレンボイムの大きさは、さうしたものとは異質で、フルトヴェングラー同樣、樂曲への批評に支へられてゐる。ちなみに、バレンボイムは、或るインタビューで、「フルトヴェングラーから學べる事は他の100人の指揮者から學べる事よりも多い。」として、特に、「彼以外のドイツの大指揮者達の音色が、較べものにならぬ程、單調である。」と指摘してゐるが、フルトヴェングラーの音色は、樂曲への批評と、和聲的な感受性との、分ち難い握手によつて、生れたものだ。
シューマンに戻る。バレンボイムは、5小節で、樂譜に書いてゐない痛烈なクレッシェンドをティンパニに與へる。一轉短調に轉じた、不安定な曲想、いはば突如襲ふ春の嵐のやうな不吉な豫感と、そこから、次の間歇的なスフォルツァートの音樂が湧出するといふ印象を、これが強めるのだ。7小節の低弦のクレッシェンド、そして、10小節前後の、ヴィオラの32部音符に與へられる搖れ、かうした内聲からの音樂への積極的な參加は、普段聽こえない内聲を、自己目的的に目立たせる、最近の才人指揮者達のやり方とはまるで意味が違ふ。最近の才人指揮者ではないが、スクロヴァチェフスキが、或る所で、「スコアに書いてある音で埋もれてしまつてゐる音を發掘するやうに響かせるのは、素敵だ。せつかく書いてあるのだから。」と言つたが、さうした、意味から切り放された無思考なスコアとの關係からは、こゝでのバレンボイムのやうな、音樂的な暗示力は、生れない。
嵐の豫感が、徐々に、穩やかな表情に鎭靜し、18小節でホルンのドルチェに導かれて、印象的にフルートが舞降りると、空氣は一變する。このフルートの歌のニュアンスの豐かさと、そのあと、20小節後半のシンコペーションの強調は、まことに喜悦に充ちてゐる。その上、バレンボイムは、21小節からの、ア・テンポの指示を無視して、まるでそつとすり足をしながら、空氣を踏むやうな纖細さで、主部へのアッチェレランドに入るのだ。
低弦の主調低音とヴィオラの單純な反覆音型が、何と憧れと豫感に滿ちて、それ自體、自足してたゆたつてゐる事だらう。このヴィオラの歌の息の長いこと! シューマンは、25小節からアッチェルランドを指示してゐるが、バレンボイムは抑へに抑へる。クレンペラーは、初めからアップテンポで單刀直入だし、バーンスタインが加速するのは30小節邊りから。バレンボイムは、テンポアップを感じさせず、むしろ踏み締めるやうに、35小節の金管のファンファーレに乘る、このテンポが上りさうで上らないまゝ、緊張を極限まで高めてゆく方法は、アッチェレランドの達人、フルトヴェングラーから、逆手に學んだものだらう。フルトヴェングラーの加速を形だけ眞似しても始らないことを、かつてさうした猿眞似をした時期のあるバレンボイムは、徐々に悟つたに違ひない。その根柢には、壓倒的な生得のリズムと和聲の鋼のやうな把握力があつて、初めて、加速は、眞に音樂的昂揚となる。
だが、抑へに抑へて、強烈なリズムの踏み締めで開始される主部は、勿論、アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェになつてゐる。この邊りの分厚い歩みは、もし先入觀なしに聽いたら、こちらがクレンペラーかと思ふ人がゐるのではないだらうか。(この項續く)